母、逝く。
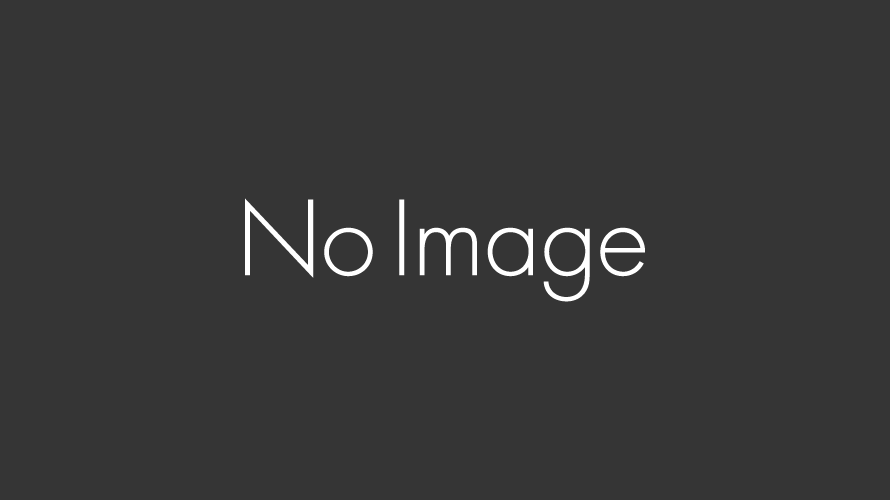
1つ前の記事で母が入院したことを書いたが、闘病むなしく6月1日9:05ごろ息を引き取った。完全に呼吸をしなくなってから、医師が病室に来て死亡確認をするまでに少し時間がかかり、死亡診断書に記載されている死亡時刻は9:12だ。
4月20日に入院してたった40日で、とくになにか手だてを打つこともなく死んでしまった。
ほぼ毎日のように病室に通い詰め、わたしの生涯の中で、母にこの世に産み落としてもらって赤子の時分にかわいがってもらったときのつぎに濃密な時間を過ごしたのではないかと思う。明らかに日々弱っていく母を見て、「死んでしまったら相当な空虚感に襲われるのではないか」と考えていたが、それは杞憂に終わった。まったくさびしくないかというと、それなりに悲しいしさびしい。しかしとても清々しく、やりきった感情のほうがいまは強い。母だって同様のはずだ。それは母の死顔を見ても一目瞭然だ。逝く2時間前、逝って5分後、逝って2時間後の顔写真を残してあるが、時間が経つにつれものすごく顔が安らかになっているのだ。死ぬ間際は明らかに苦しそうな顔をし、息を引き取ってから見る見るうちに顔がやすらかになっていて、しまいには笑顔だ。しかし残念なことにそれに反比例して体温はどんどん下がっていってしまった。
その安らかな顔をみんなにも見てもらいたいが、これはわたしと母との大切な思い出としたい。
以後、時系列で入院から亡くなるまでのエピソードを記載していく。
4月20日~4月30日
1つ前の記事をご参照ください。
5月1日~5月20日
いわゆるゴールデンウィークに突入し、会社のみんなに迷惑をかけることなく母の入院する病院へ通うことができる。このゴールデンウィークは、4月末にいろいろと検査した結果を伝えられるという大きなイベントが予定されていた。
5月2日の最初の休みの日、さっそくに主治医から時間を押さえられ病気について話を聞くことに。病名は以下の写真のとおりだ。

想像以上に悪い結果となっていた。仮に癌を除くことができたとしても、リンパに転移している以上予後はよさそうではない。家族として真っ先に質問することは、これだ。
「治るのでしょうか?治らないにしてもどのくらい生きられるのでしょうか?」
これしか聞くことがない。骨盤内のほぼ全域が癌に蝕まれ、詳しいことを聞かなくても相当に悪いことは想像に難くない。主治医曰く
「難しいですね。年単位で生きるということはできないです。いまの感じだと3~6ヶ月くらいでしょう。治療については、お母さんはとても痩せていて、抗がん剤の治療というのはいまはできないです。もう少し体力がついてきたら挑戦してみるということは可能です。」
感情的な強い衝動を受けることはとくになく、仕事の中でものの説明を淡々と聞いている感じになった。おそらく、あまりに強烈な内容すぎてしっかりと理解できずに感情的にならなかったのではないかと思う。しかし、起こってしまったことは仕方がない、残っている時間を最大限楽しく充実した時間を過ごすほかないと頭を切り替えた。
ちなみに、余命宣告というのは「治せません」という医師の白旗宣言なのだそうだ。
この手の病名告知は、本人に言うか否かで1つの選択があると思うが、わたしのポリシーは「自分の身体のことは自分でしっかりと理解すべき」というポリシーである。だからインフォームドコンセントとかもしばらく前からはやっているのだと思う。そのポリシーの基、母も同じ説明を主治医から聞いているのだが、どのような気持ちで聞いていたのだろう。わたし以上に無関心だったのか、わたしに対して病気について質問してきたことはない。亡くなるちょっと前に「わたしの病気治るの?」なんて聞いてきたことはあったけれど…。

ふだんわたしは料理なんかほとんどしない(今年に入ってからちょっとずつするようになっているけど)のだが、わたしがたまに作った煮魚をおいしいと母は食べていて「また食べたい」というので、作って持って行った。とにかく病院のご飯はおいしくないらしく、ぜんぜん食べないのだ。写真はチャーハンとかれいの煮付け。自分でいうのもおかしいが、それなりにおいしい。
これから体力をつけようというときに、ものを口から入れないというは致命的。なんでもいいから食べさせたい一心でいろいろと取り組んだ。

さらにひとりだとほとんど食べないようなので、休みの日の昼と夜は弁当を作って病室に持参した。そして配膳される病院食といっしょにお互いに好きなものをつつきあいながら食事を楽しんだ。

テレビでふなっしーを見たのか「ふなちゃん、ふなちゃん」なんていうので、ふなっしーのキャラ弁も作った。この卵のなかはきちんとチキンライスになっていて、オムライスのそれである。
この20日間は本当に苛酷で、15日くらいからものを食べなくなってしまった。ゼリーやプリンなどのやわらかいものをスプーンで口元に持っていけば食べるものの、自発的にものを食べられない状態だ。それに比例してみるみる痩せていっている。
5月21日~5月31日
このころから病室に見舞いに行ってもほとんど寝てばかり。起きていても夢うつつで意味のわからないことを言ってみたり、その場にいない人を呼んでみたりとだいぶ混濁している様子。これは癌の疼痛抑制のために利用しているモルヒネのせいらしく、副作用でとにかく眠くなったり、幻覚を見たりするそうだ。
病院からのレコメンドで「ホスピスに移してみてはどうか?」といわれたので、ホスピスの病棟を管理しているえらい医師と面談した。最初の質問はこれだ。
「ホスピスってどういうところだと認識されてますか?」
生活の中で、なんとなく触れたメディアからの情報だと、”余生をゆっくりと過ごすところ”のようなイメージだが、「ホスピスとは」というような定義としてはしっかりと認識していない。
その医師曰く、
「ホスピスで余生をゆっくり過ごすことに間違いはない。ゆっくり過ごすために、いま病室でつけられているいろんなチューブとかも外します。本人がおにぎりを食べたいといったとき、そのおにぎり1つ食べるのに1時間かかるなら1時間つきっきりで食べることを手伝います。急性期の病棟ではそうはいきません。ほかの患者さんが来たらそっちに行かないといけない。ホスピスはそういうところです。これにはいいとか悪いとか人それぞれ価値基準があるから、お母様やご家族とよく話し合って決めてください。」
んー、治療をしないということは本当に亡くなることを待つだけになる。家族としては治らないにしても”なんらかの治療”にどうしても期待せざるを得ない。そうなると必然ホスピスという選択肢はなくなる。しかしながら、病院側としては経営的に急性期病棟からは出て行ってもらいたいであろう。どうしたものか…。
5月24日になると、いよいよ酸素濃度が下がってきたとのことで酸素のチューブを鼻に入れられていた。これはもう覚悟せざるを得ない状況だ。

こんなことを掌に書き込んだ。掌に落書きなんかされたらくすぐったくて文句を言われそうなものだが、残念ながらそういうリアクションはない。もうすべての動作を他人に委ねるほかない状態だ。
5月28日、通常どおり会社で勤務していると病院から電話がかかってきた。
「あまり調子がよくなく、個室も空いているのでそちらにお母さんを移しましたので、つぎにお越しの際には気を付けてください」
とのこと。おいおい、個室に移るって、もう死ぬ直前じゃないか。

夜、会社帰りに寄ってみるととても立派な個室に移動されていた。看護師さんから泊まっていってもいいといわれたが、家が近いので「なにかあったら電話ください」と告げ病室をあとにした。
5月29日6時半、鳴って欲しくはない電話が鳴り、シャワーを浴びて病室に到着する。どうも酸素と血圧が下がってきて、さらに尿量も少ないとのこと。どうにもこうにももう本当に難しい状態になっている。もはや逆転満塁ホームランなんてことは望まないから、とりあえず死に目にだけはあえるようにしておきたいと思い、この日は会社を休むことにした。が、その後とくに変調はなくこの日はそのままゆっくりと過ぎて行った。
運よく週末を迎えることができ、この週末には来てもらいたい人にはとにかく来てもらって最期のあいさつをしてもらうようにした。来客者のアテンドにこちらも疲れないわけではないけど、もうそのようなことを言っていられない状況であることは人一倍理解している。
個室に移ったので、母が好きだった音楽などもYoutubeで再生し、ひたすらに最期のときを楽しんでもらえるように土日を過ごした。
6月1日
前夜、母の弟たち、つまりわたしの叔父たちが帰り際に「なんか後ろ髪引かれる思いだけど、明日から月曜日で仕事もあるから一度帰るね」なんて言っていた。わたしは自宅が近いので看護師さんにまた「なにかあったら電話ください」といい、昨夜は自宅に帰ることにした。
そして先日と同様に「電話が鳴りませんように」と思いながら就寝したのだが、またもや朝6:30ごろに鳴って欲しくはない電話で起こされることになる。
「お母さんの血圧が上が70、酸素濃度も90前後に落ちてきています。すぐにどうということはないと思いますが、念のため病院に来てください」
いよいよ覚悟を決めた。どう考えたってよくなりようがない状態なのだ。どんな状態であれ生きていてほしい。でも、本人もわたしもこの生活がずっと続くことはもちろん望んでいるものではない。これまでの生涯においてこんなにも葛藤したことがあっただろうか。奇跡が起きて、自宅に帰ってきて療養できるくらいまでになるのであればいいのだが、この数日間の状態を見ている限りではまず無理だ。
「すぐにどうなることではない」ということなので、とりあえずシャワーを浴びて、少しばかり家の中を片付けて病院に行くことにした。この時点でわたしは”長丁場になる”ことを無意識のうちに悟っていたのかもしれない。
シャワーから出て近所のコンビニで朝食を買い病室に向かう。そのくらいの冷静さは持ち合わせていた。病室に着くと昨夜とほぼ変わらない母がいるのだが、どうにもこうにもアゴを上げての呼吸となっていて苦しそう。看護師から「ほかにご家族の方はいらっしゃいませんか?」との質問が。いままでこんな質問をされたことがないので、もういよいよ旅立つ準備をすべきなのだろう。わたしには弟がいるので、弟には病院に来る途中に電話ですぐに来るように伝えておいた。なので「あと1時間もすれば来ると思います。そのくらいよくない感じですか?」と質問すると
「詳しいことは先生から聞いてほしいですが、このくらいの状況になると人によって急に落ちていったり、ゆったりと落ちて行ったりとそれぞれになります。弟さん間に合うといいんですけどね」
最後の”弟さん間に合うといいんですけどね”がもう決定打だ。おそらく母はこの数時間のうちに死ぬ。今日がXデーになることはほぼ間違いないだろう。しかし、数日前から葬儀屋などにも連絡して段取りはきちんとできていたので、最期をしっかりと見届けることに備える。
9時過ぎ、母の呼吸は大きく回数の少ないものに変わっていった。一瞬止まったかと思ったら、2度ほどグッグッと歯を食いしばり、そのあとで呼吸が止まった。それはまさにぜんまい仕掛けのおもちゃのぜんまいが、のびきったかのような動作であった。
バイタルが無線でナースステーションに飛んでいるので、すべての値がフラットになったことを知らせるアラームでも鳴ったのだろう。ナースステーションから数人の看護師さんがやってきた。いつもお世話になっている面々だ。
しばらくして医師がやってきて死亡診断をしてくれた。あっけない。66年間の歴史を背負ってきた人生の最期が、バイタル、脈、瞳孔の確認だけで
「9:12、ご臨終です」
の一言で終わってしまうのだ。
その医師の臨終の合図から”喪主”となったわたしは看護師に呼び出され、「お迎えの業者さんの当ては大丈夫ですか?何時に来られますか?」ともう退去の話になる。先ほどまで生死の行き来をしていたドラマはどこへやら、一気に事務的になる。正直、悲しんでいる隙すら与えられない。しかし却ってそれがいいのかもしれないなと考え直し、一心不乱に葬儀の手続きに入る。
葬儀業者さんが迎えに来るまでの間、わたしは弟といっしょに数珠を買いに行き、そしてほか弁を買って自分らを慰めた。
病室に戻ると、母はとてもきれいに死化粧を施されて、ここ数年で最もきれいになっていたのではないだろうか。買ってきたほか弁を弟と食べながら、
「小学生のとき、オババは土日はいつもお弁当を作ってくれてたよね。買ってくる弁当だと(オババは)のり弁が好きだったよね。」※わたしは母を”オババ”と呼ぶ。
なんて思い出話で盛り上がるも胸が苦しくなる。たった39年間しかいっしょにいられなかったけど、細かい思い出があるのだ。弟は当然私より若いので、35年しか母といっしょにいられなかったのだ。それを思うと不憫でまた胸が苦しくなった。
母はまだ意識があって会話ができるとき「家に帰りたいなぁ」とよく言っていたので、葬儀業者さんには無理を言い、亡骸を自宅に連れ帰ってもらった。ここで丸3日をとも過ごし、今日6月4日にぶじ告別式を終え本プロジェクトは終了した。
ねぇ、お母さん。お母さんの人生は幸せだった?
ぼくはお母さんの子供に産まれて、そして39年間一緒に過ごせてとても幸せだったよ。ありがとう。
おわりに
わたしはいま介護業界に勤めており、人の生と死や介護・看護について普通の人よりは身近に過ごしているつもりだった。だからか、いろいろなことを冷静に受け止めることができ、病院の手配、治療方針に関する医療従事者とのコミュニケーション、セカンドオピニオンの手配、ホスピス(緩和ケア)に対する心構え、死に対する心構えなどなどたくさんのことをすることができた。これはまわりの仲間たちのサポートももちろんだが、自分が保有している情報量に比例して対応力というものが発揮されるのではないかと考えている。
もし、同様にお困りの方がいらっしゃれば、ひたすらに情報を集めて正しい対応をすることをおすすめする。インターネット上の情報もいいが、玉石混交なのでできれば知り合いがよいだろう。わたしが力になれるのであれば、コメント欄からご相談いただければできる限りのことはやらせていただきたいと思っています。
- 前の記事

母、病に伏す。 2015.04.20
- 次の記事

東急世田谷線を歩く。 2015.10.24